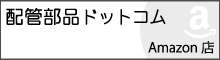パイプの歴史
公開日:
:
配管とは
下川義雄氏の『日本鉄鋼技術史』(アグネ技術センター)によると、日本で初めて鋼管が作られたのは1905(明治38)年のこと。呉工廠が製造した艦艇装備用のものでした。その後、1912年に日本鋼管(現JFEスチール)が設立されて国産鋼管の製造が始まり、第1次世界大戦で輸入品が途絶えたことにより、急速に国産品による代替が進みました。
当時の給水管は3インチ以上は鋳鉄管、それより小径のものは鉛管が用いられていました。鋳鉄管は1890年代に国産化が始まり、明治末期にはほぼ国産品で代替されていました。鋳鉄管メーカーには、1887年創業の釜石鉱山田中製鉄所(現新日鐵住金釜石製鐵所)、1889年創業の久保田鉄工所(現クボタ)、1893年創業の永瀬鉄工所、1906年創業の栗本鐵工所など、今も大手として存続するメーカーがありました。また鉛管メーカーとしては、1884年創業の古河電気工業、1892年創業の泉鉛管製造所、1899年創業の日本鉛管製造所などが製造を行いました。
排水管は、明治初期には手作り鉛管、銅管を用いていたものが、鉛管は特に高価だったことから徐々に鋳鉄管に代替され、また腐食に強いことから、陶管も多く使われ、横浜外国人居留地の下水道用に最初の国産陶管が使われました。1872年に常滑の鯉江方寿が、英国からの輸入品を参考に製造したものが初めての規格品かつ、初めての大量生産品でもありました。ただ、陶管は地震などで破損する欠点があり、より強固なものとしてレンガが採用されることもありました。1884年に築造された東京「神田下水」で、現在もほぼ昔の形のまま使用されています。一方、配管に銅管が使われたのは1923年、大阪医大附属病院で給湯用に使用されたのが始まりといわれています。水道用には、1932年に東京市水道局が、1937年に大阪市水道局が銅管を採用しています。
PC
最後までお読み頂き誠にありがとうございます。
お手間でなければぜひ本記事のご紹介をお願いします。関連記事
-

-
配管を構成する部材たち
配管は多くの部材を使って製作されます。パイプやホースには材質別に、金属管に鋳鉄、鋼、ステンレス鋼、銅
-
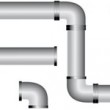
-
配管ってそもそもなに?
第1回目は「配管とはなにか」を掘り下げて考えてみたいと思います。 皆さんは「配管」と聞くと何を思い浮
-

-
配管における流体とは何か
物体は通常、固体・液体・気体の3つに分類されますが、そのうち液体と気体には容易に変形するという性質が
PC
- PREV
- 第17回「日本水大賞」決定 大賞に宮古工業高校
- NEXT
- ホースの歴史