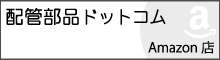17年度末 建設許可業者数微減 管工事業は2年連続増
公開日:
:
業界ニュース
国土交通省がこのほど公表した2017年度末(18年3月末)の建設業許可業者数は前年度末比0.1%減となり、16年度(1.1%減)、17年度(0.5%減)に続いて減少した。ただ、建設業許可の有効期間の関係で、16~18年度の3年間は許可の更新期を迎える業者数が多い年度に当たっていることから失効業者数も多く、実質は横ばい程度にとどまったものとみられる。
管工事業は0.6%の増加(486業者増)で、前年度末(0.3%増)に続いて増加した。過去十数年のピーク(04年度末)の9割程度の水準にある。
建設業の許可業者数は、99年度末をピークに減少を続けてきた。08、09年度末も表面上は微増となったが、失効数が少なかったことによるもので実質減少したものとみられ、以降、毎年減少が続き、13年度末でようやく0.2%増と下げ止まり、14度末も0.5%増となったが、15年度末は再び1.1%減、16年度末0.5%減、17年度末で0.1%減(565業者減)の46万4889業者となっている。
17年度中に新規に建設業許可を取得した業者は2万1035業者で、前年度比4.0%増(813業者増)となった。これに対し、建設業許可が失効した業者は2万1600業者で、前年度比3.6%減(803業者減)となった。うち、廃業は9601業者(前年度比4.3%減=431業者減)、失効した業者は1万1999業者(同3.0%減=372業者減)であった。
17年度末の一般建設業許可業者は0.2%減(1040業者減)で、ピーク(99年度末)から約23%減、特定建設業許可業者は1.3%増(574業者増)で、ピーク(04年度末)から約12%減となっている。
管工事、水道施設、機械機具設置、消防施設の各業種をみると、管工事業の許可業者数は0.6%増の8万4454業者。13年度末0.3%増、14年度末0.4%増のあと、15度末は0.6%減といったん減少したが、16年度末0.3%増と再び増加、17年度で2年連続増となった。管工事業許可業者は80年ごろまで大幅増加が続き、その後減少に転じ、02年度以降は減少基調が鮮明となり、13年度末で下げ止まった。以降も微増、微減を繰り返し、17年度末でピークの04年度末(9万2350業者)に比べ約1割減(7896業者減)の水準にとどまっている。
水道施設業は8万2597業者で、16年度末(0.3%増)に続いて増加した。機械器具設置業の許可業者は2万1685業者、2.2%増と11年連続して増加している。消防施設業の許可業者は1万5063業者、0.5%増と16年度末(0.1%増)に続いて増加した。
管材新聞 2018年6月27日 第1742号より抜粋
PC
最後までお読み頂き誠にありがとうございます。
お手間でなければぜひ本記事のご紹介をお願いします。関連記事
-
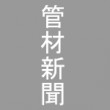
-
ノーリツ 外国人に入浴意識調査 ハイテク機能が人気
ノーリツは、日本文化の特長のひとつである「おふろ」について、日本在住の外国人(英語話者)を対象に、入
-
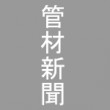
-
IDE研究所分析 設備配管の管種選定動向 樹脂ライニング管が依然高シェア
配管の研究調査と鋼管業界への支援活動を推進しているIDE研究所はこのほど、商業建築の空調衛生設備配管
-
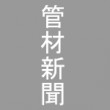
-
前澤給装工業 給水装置値上げ 31年4月から10%以上
前澤給装工業(本社・東京都目黒区)はこのほど、来年4月1日出荷分から水道用給水装置製品全般の価格改定
-

-
TOTO ネオレストCMがW受賞 ベン親子が好評
TOTOが15年1月から全国放映しているウォシュレット一体形便器「ネオレスト AH/RH」の
-
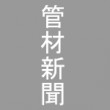
-
18年大手建設50社受注 9年ぶりに前年割り込む民間工事も4年ぶり下落
国土交通省がまとめた2018年(1~12月)の建設大手50社の工事受注総額は、前年比3.8%減少の1
-

-
フローバル 絶縁工具セット販売開始
継手・バルブ・ホース金具など配管部品専門商社のフローバルはこのほど、電設工事作業で使用頻度の高い絶縁
-
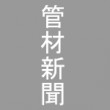
-
2016年度 下請法違反指導件数 7年連続で過去最多更新
公正取引委員会がこのほど公表した2016年度の下請法違反による指導件数は6302件(別に勧告11件)
-
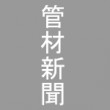
-
TOTO 台付シングル混合水栓4シリーズが『レッドドット・デザイン賞2019』受賞
TOTOの台付シングル混合水栓「GMシリーズ」「ZAシリーズ」「GEシリーズ」「GCシリーズ」の4シ
-
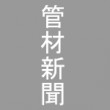
-
15年度上期建設工事受注 前年度比7%増 建築・建築設備堅調
国土交通省の建設工事受注動態統計調査による2015年度上半期(4~9月)の建設工事受注額は、前年同期
-
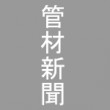
-
JFEスチール 国内向け鋼管全品種を5%値上げ
JFEスチール鋼管営業部はこのほど、国内向け鋼管全品種の値上げを発表した。 鍛接管、電縫管、継目無